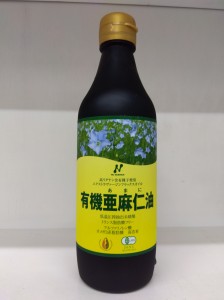花粉症が心配な方、ご相談ください!
花粉が飛び始める前に・・・
〇免疫のバランスケアーに良い生薬系のサプリメントがあります。これを早くから続けて服用すると予防になります。ひどかった花粉症が劇的に楽になった方も多くおられます。
〇良質のクマ笹エキスや大麦若葉エキスには、体液をアルカリ化しアレルギー反応や炎症を軽くする働きがあります。花粉症の症状を軽くするのに効果的です。体質改善にもなりますので、継続して服用されることをお勧めします。
〇EPAには抗炎症作用と抗アレルギー作用があります。普段からサプリメントで十分な量を摂っておくと花粉症が楽になります。
花粉が飛び始めたら、からだの中に入る花粉を減らす工夫をしましょう。
日ごろから花粉飛散の情報をチェック/ 飛散が多いときはできるだけ外出を控える/ 外出時にはマスクやメガネを着用する/ 外出時には毛織物などのコートは避ける/ 帰宅時は玄関前で衣服などの花粉を払う/ 帰宅後は手洗い・うがいや洗顔を励行/ こまめに掃除を行い必要なら空気清浄機を/ 部屋の喚起をする際はカーテンを閉める/ 布団や洗濯物などはできるだけ外に干さない/ 食生活を見直して規則正しい生活をする
花粉が身体についてしまったら・・・
〇鼻うがい、目洗いで、花粉を洗い流しましょう。
〇皮膚についた花粉も影響します。顔はもちろん、身体についた花粉も洗い流すことが大切です。
花粉症の症状が出てしまったら・・・
〇つらい鼻炎も漢方薬で楽になります。鼻炎症状を改善する漢方薬には10種類近くありますので、くれぐれも症状と身体にあった漢方薬を服用なさってください。
〇ひどい鼻詰まりと目のかゆみには、点鼻薬と点眼薬を上手に使うと直接的に症状を取ってくれるので効果的です。
放っておくと、花粉症は年々ひどくなります。今年の症状をひどくしてしまうと、来年は炎症が起きやすくなりもっと強く出ることがわかっています。来年以降をひどくしないためにも、今の症状を軽くしておくことが大切です。
~薬剤師 鳥居英勝~