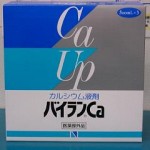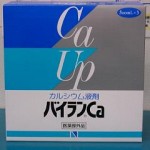カルシウムは食事から摂取することが大切ですが、
カルシウムは食事から摂取することが大切ですが、
必要量を満たすのは容易ではありません。
食事で摂りきれないカルシウムを十分量摂取するには、「カルシウム剤」がお薦めです。
当店では、「身体に吸収されやすいように電解してイオン化したカルシウム剤」や、
「腸からの吸収が良くなるように活性型ビタミンDを配合したカルシウム剤」をお薦め
しています。
食品からカルシウムを多く摂取するには、「海藻類」がお薦めです。
牛乳はカルシウムを多く含むことで知られていますが、異種蛋白を多く含む牛乳を大量に
飲むと身体の液性が酸性に傾き、それを中和するのに骨のカルシウムが溶け出すので、
結果的に骨がもろくなるというデータが出ています。
牛乳をたくさん飲むアメリカ人の女性は、アメリカ人と比較して余り飲まない日本人に比べて、
骨粗鬆症になる割合が高いという臨床データからも納得できます。
牛乳は、嗜好品として毎日少量を飲む程度ならば全く問題ありませんが、カルシウムを摂る
目的で大量を飲み続けるのは間違いです。
成長期の子供や妊娠授乳期の婦人、閉経後の女性などは、積極的にカルシウムを摂る必要が
あるといわれています。
また、カルシウムは骨粗鬆症の予防はもちろんのこと、アレルギー体質の改善やイライラや動脈硬化の
予防にもなると言われています。
また最近の研究では、「血圧が高い方がカルシウムを積極的に摂ると、血圧が正常に近づく」という
発表もされています。
毎日の健康を保つために、カルシウムを積極的に摂取することをお薦めします。
~薬剤師 鳥居英勝~